他ジャンルからソルトにトライするアングラーにとってハードルとなるのがラインシステム。ヤップ君もまだ苦手意識がある。今回はラインシステムの基礎を復習してみよう。
本記事ではアフィリエイトプラグラムを利用しています。
釣り経験はあるものの、ビギナーレベルから抜け出せずにいる30代男性。オフショアゲームでエキスパートを目指すべく奮闘中。東京都在住。
徳永兼三(とくなが・けんぞう) 東京都大田区でプロショップ『BASS MATE』を経営するエキスパートアングラー。バスフィッシングからマグロ、GTといったビッグゲームまで幅広くこなし、国内外のフィールドに精通。これまでに数々のレコードフィッシュを釣り上げている。
池貝雅俊(いけがい・まさとし) バスフィッシング、シーバス、近海のオフショアなど関東周辺のルアーゲーム全般に造詣の深いバスメイトの店長。タックルに関する知識も豊富で、店内で扱う商品在庫のすべてを把握していると言っても過言ではない。
PEラインとリーダーの結束をマスターすれば世界が広がる!
徳永さんこんにちは。毎日暑いですね。
そうですね。やあ、ヤップ君。この一年で関東のオフショアゲームを一通り体験してもらって、だいぶ上達したんじゃないですか。
おかげさまでオフショアの苦手意識はなくなりました。でもいまだに苦手なのがPEラインとリーダーの結束、ラインシステムなんです。
たしかに、バスフィッシングからソルトに来る人にとってはひとつのハードルと言えるかもしれませんね。最近ではフレッシュウォーターの釣りでもPEラインが普及しつつありますが、それでも複雑なノットに拒否感を持つ人はいらっしゃるようです。
ホントに、あれさえなければソルトゲームも楽なんですけどねえ。
じゃあせっかくだから、今日はソルトゲームのラインシステムについて復習してみましょうか。まず、なぜリーダーが必要か、ヤップ君は知ってますよね?
簡単に言えば、メインラインの強度を補って大きな魚を釣るってことですよね。
そうです。メインライン、すなわちPEは細くて強いのが特長ですが、逆に細いぶん、衝撃や摩擦に対する耐久性に欠けます。それをリーダーで補うわけですね。それともうひとつ、ナイロンやフロロは透明で魚から見えにくいので、メインラインの先に結ぶことで喰わせやすくなるメリットもあります。
強度を補うための役割と、ハリスとしての役割の二つがあるってことですか。実際、そのことによって以前とは何がどう変わったんですか?
一番はより大きな魚、より遠いポイント、より深いポイントを攻略できるようになったことですね。ナイロンの時代は水深100mを超えるディープレンジをジギングで狙うことは考えられませんでした。GT、ヒラマサ、マグロもいまでこそルアーフィッシングのターゲットですが、それらはすべてPEラインとそれを生かすシステムの登場によって狙えるようになったと言っても過言ではありません。
それはPEラインの伸びが少ないからですか?
もちろんそれもありますが、ナイロンに比べて細いラインを使えることが大きいですね。ラインが細ければより多くのラインをリールに巻き込むことができるうえ、抵抗が減るためルアーの飛距離が圧倒的に伸び、ジギングでも深いレンジを攻めやすくなります。
ナイロンとPEでは、具体的にはどのくらい巻き量の差があるんだろう?
昔はショアからヒラマサを狙うにも、船からGTを狙うにも、ナイロンの20~30lbが限界でした。それをリールに巻こうと思うと、当時の大型リールでも200m~250mしか入らなかったんです。ところがPEの30lbは1.5号から2号くらいですから、同じサイズのリールに500m以上入ってしまいます。
なんと倍以上ですか! それほど差があるとは。
ナイロンでやるなら最低でも50~60lbの強度が必要ですが、そんな太い糸をストックできるリールはありませんし、あったとしても重い、飛ばない、沈まない、ルアーも動かない、ヒットしても一気にラインを持って行かれるなど、いいことはありません。
魚のサイズに対するラインの強度と、空気中や水中でのライン抵抗を考えたときに、両方を同時に満たすことは不可能だったんですね。
そう、オフショアの釣りをやっていく上でラインシステムを絶対にマスターしておくべきというのは、そういうことなんです。
PEラインは平滑性や耐摩耗性が年々進化
よくわかりました。ところで徳永さん、PEラインには4本編み、8本編みなどいろいろ規格がありますが、価格もいろいろです。やっぱり高いものを買ったほうがいいですか?
いまは8本と4本では価格も性能もあまり差はありません。それより原糸の段階での細さとか、編み込みの工法とか、製造技術の進化に注目してもらうほうがいいですね。こだわった製品はライン表面のコーティングや平滑性、耐摩耗性という部分に優れていて、必然的に高価になります。
差はけっこう大きいですか?
大物釣りの場合はとくにそうした違いが顕著に出るので、しっかりしたラインを選ぶほうが安心です。ただ、ラインの消耗が激しい釣りではあえて高価なラインを使わず、手ごろな価格のラインを頻繁に巻き替えるというのもおすすめです。
PEラインはナイロンとかフロロに比べて劣化がわかりにくいと思うんですけど、交換のタイミングはどうやって判断するんですか?
たとえば遠征のビッグゲームの場合、一日の釣りでキャスト回数は100の単位。3日やれば1000投近く投げていることもあります。これだけ投げると、たとえ魚がヒットしなくてもラインには相当な負荷が掛かっているので、遠征から帰ったときが巻き替えるタイミングです。
遠征ではなくても数回の釣行でそのくらいはキャストしているかも。
釣行回数が少ない方はキャスト回数も少ないかもしれませんが、その間には紫外線劣化もあるので、少なくとも半年とか、年が変わったら新しく巻き替えるとか、期間を決めて定期的に交換することをおすすめします。
PEは毛羽立ちが目立ってきたら巻き替えるべきとも聞きますが・・・
いやいや、それはもう限界を超えています。毛羽立ちが目に見えるなら本来の強度は絶対に出ていません。それでもターゲットに対してオーバースペックのラインなら問題ないこともありますが、そうなる前に交換すべきですね。
ナイロンと違って長持ちすると思っていたけど、消耗品であることに変わりはないですもんね。
リーダーの強さと長さの基準は?
じゃあ次に、リーダーの素材の特徴についておさらいしてみましょう。ヤップ君はリーダーを選ぶとき、ナイロンとフロロをどのように使い分けていますか?
あまり深く考えてないかも。表層を釣るときはナイロン、水中を釣るときはフロロってくらいですかね。
なるほど、そういう人も多いですね。私の場合、キャスティングでは30lbまではフロロ、それを超えたらナイロンという使い分けをしています。ジギングでは100lbより太くなったらナイロンを使います。フロロは表面が硬く根ズレに強いのが特長ですが、太くなるほどその硬さがデメリットになるんです。
でもナイロンじゃ弱いんじゃないですか?
そんなことはありません。ナイロンはしなやかだし、太い号数なら硬さと耐久性も十分にありますよ。
ボクはリーダーの太さもときどき迷うことがあるんですが、メインラインとショックリーダーのベストな組み合わせというか、『リーダーはPEの号数の〇倍』みたいな方程式はあるんですか?
以前はおおまかな目安があったかもしれないですが、いまはそういうものは聞きませんね。あえて基準というなら、その釣りやポイントに精通したエキスパートのタックルを参考にすると良いでしょう。
徳永さんは何をもとにリーダーの強度を絞り込んでいくんですか?
私の場合は魚の大きさとか、釣り場の条件を考慮したうえでのミニマム強度が目安です。マックス強度にしたらどこまでも強くなってしまいますし、強さと同時に釣りやすさも考えないといけませんから。
使いやすさと必要な強度の最大公約数的なところを探すってことか。
そういうことです。だから同じ釣りでも状況によってはラインシステムを変えることがあります。最も極端な例は、デカい魚が小さなベイトを食っているパターンですね。この場合、ヒットする魚のサイズに合わせてライン号数を太くすると小型ルアーをキャストできず、小さなルアーに合わせて細くしてしまうと今度は魚のパワーや根ズレに耐えられない。最終的にそのバランスをどこに持って行くかということですね。
リーダーの長さは短いほうがいいんですか? それとも長く取るべきですか?
基本的には魚の体長より長ければOKです。たとえばシーバスなら、通常釣れるサイズは最長で1mですから、その長さがあれば十分ということです。
それはリーダーが魚体に触れたときの対策ってことですよね?
はい。あとはそれを基準に海底の地形や根ズレなどの条件を加味して調整します。
ノットは結びやすく安定した強度を出せることが大事
PEとリーダーを結ぶノットにもいろいろありますが、徳永さんはいろいろなノットを使い分けていますか?
いまはすべてFGノットでやっています。自分が一番慣れていて、かつ安定した強度を出せるので、ほかのノットを使う必要がないとも言えます。
たしかに自信のあるノットをひとつ持っていると強そうだなあ。ほかにはどんなノットがありましたっけ?
代表的なのはFGノット、PRノット、ミッドノットの3パターンです。PRノットは一定のテンションで長い距離を結べるのが特徴で、硬く喰い込みにくいフロロを使ったシステムに適しています。ジギングでPRノットを使う人が多いのはそのためです。ただ強度を出すためには一定の長さが必要なので、キャスティングではデメリットになることもあります。
FGノットは徳永さん的に強度を出しやすいと言われていましたが、どんなノットですか。
FGノットは締め込みをダブルで絡めていくので、結び目を短くできるのが特長です。そのためキャスティングでもジギングでも使いやすく、エアノットができにくいというメリットがあります。
エアノットはどうしてできるんですか?
キャストの際に結び目部分がガイド等に当たって失速すると、滑りの良いPEはリーダーを追い越して飛んでいこうとする。これがエアノットの原因です。その意味でFGは非常に優れたノットと言えます。
強度的にはどのノットが優れているんですか?
厳密に測るとミッドノットが一番強いと言われていますが、ミッドノットは工程が緻密で手間がかかる点が面倒と言えば面倒。揺れる船の上で結び直す際の簡便性ではほかのノットに劣ります。ただ、ちゃんと結べばどのノットも十分に強いので、先ほども言ったように自分的に信頼できるノットをひとつ持っておくことが大事です。
いままではなんとなく気分でシステムを組んでいましたが、やっぱりちゃんとマスターしないといけませんね。次の釣行までにはもう少し時間があるので、得意と言えるノットができるまでもう一度しっかり練習してみます。
釣り人にとってノットは基本中の基本。魚とアングラーを結ぶのは一本の糸だけですからね。はじめは面倒でも、マスターすればいろいろなことができるようになって世界が広がるし、デッカイ魚を釣り上げるチャンスも広がりますよ。
いくら良いタックルを揃えても、ラインシステムをおろそかにして一生に一度の大物を逃したらシャレにならないですもんね・・・。
ラインシステムは釣り場に行かなくても出来るプラクティス。空いた時間に楽しみながらマスターしてください。
■取材・文/高橋大河 Taiga Takahashi
◎INFORMATION
フィッシングプロショップ バスメイト
所在地:東京都大田区東矢口3-6-7
TEL:03-3735-0200
定休日:毎週月曜日
HPアドレス:www.bassmate.co.jp

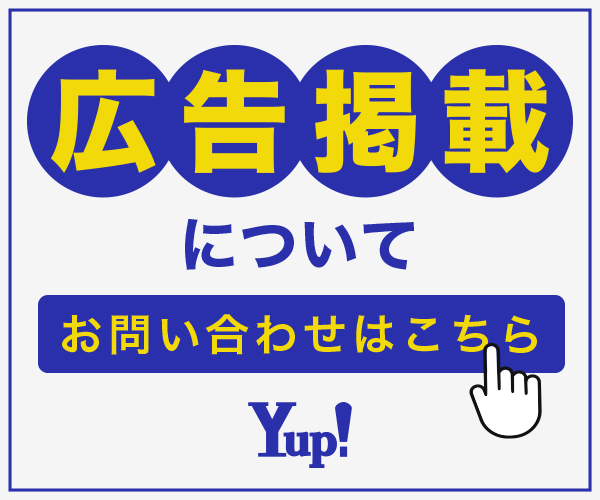




コメント